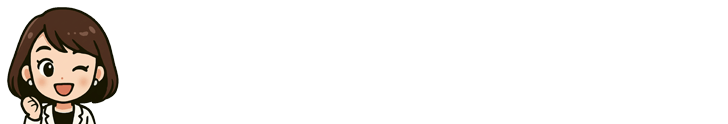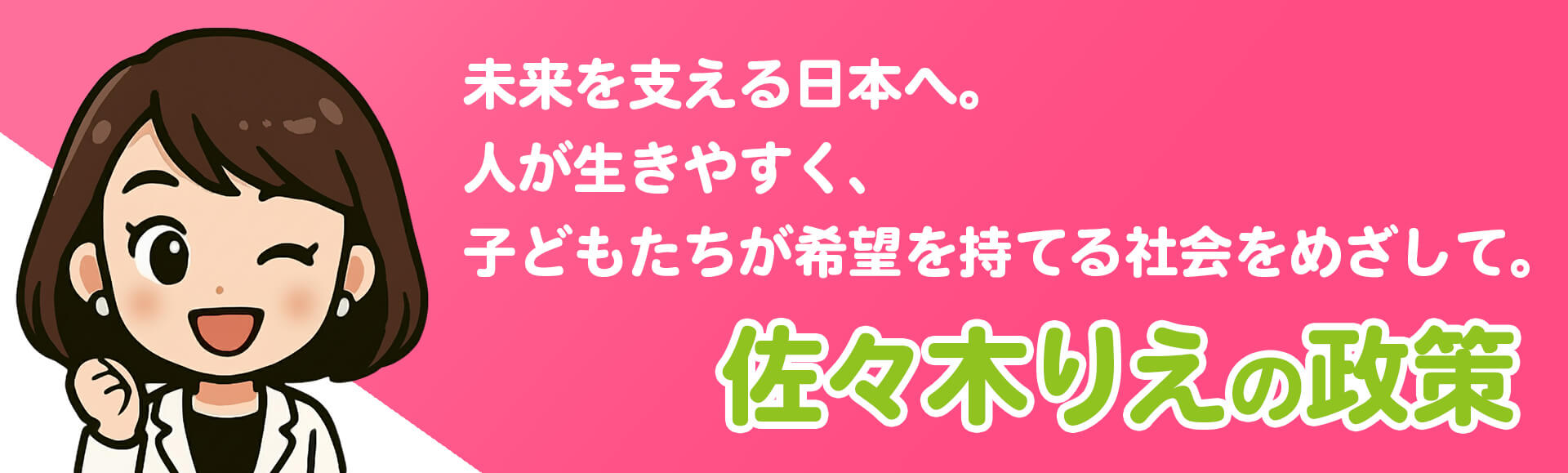
1.特別養子縁組支援の拡充
すべての子どもに温かい家庭と希望ある未来を。
少子化が進む一方で、赤ちゃんの虐待死という悲しいニュースが後を絶ちません。「育てられない親が罪に追い込まれる社会」ではなく、「安心して子を託せる社会」を。
そのために、安心して赤ちゃんを預けられる“ギブアップ”の仕組み、いわゆる”赤ちゃんポスト”の選択肢を社会が提供するべきだと考えています。
そして、目の前の子どもの命を救うために、特別養子縁組への支援拡充を進めていきます。
不妊治療に続く“第二の選択肢”として、特別養子縁組の制度を整えます。
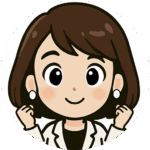
すべての子どもに達に温かい家庭を。子どもを望みながら困難のある家庭に、不妊治療とともに、特別養子縁組を選択肢として考えていただける社会になってほしいと考えています。
2.副首都構想
災害に強く、分散型で地域が成長する日本へ。
今、日本は”人”も”金”も東京一極集中が加速し、地方の過疎化が深刻化しています。日本全体の人口減少が進む中で、首都圏だけが膨張し続けるのは、国全体のリスクでもあります。
この状態を放置すれば、日本の成長が阻害されるだけでなく、ひとたび災害等が発生すれば、我が国の国家機能が麻痺する危険があります。
災害や有事に備え、国の中枢機能を分散し、複数の地域に成長エンジンを持たせる。それが「副首都構想」です。
大阪に限らず、日本各地に副首都としての権限を持つ自治体を誕生させる後押しを整備します。
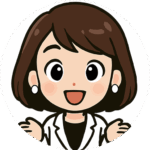
日本の国土全体で再び日本を成長させましょう!
3.特区民泊の健全化
観光と住民が共存できる大阪へ。
大阪における特区民泊は、観光振興や地域経済に貢献する一方で、違法運営・騒音・ごみ問題など課題も多く抱えているのが現状です。
大阪市では、「違法民泊撲滅チーム」を立ち上げることにより、新規事業者の受付を一旦停止し、約6,000件以上の問題を是正、全施設を対象にさらなる調査を進めています。
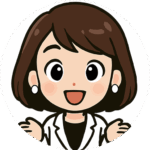
経営管理ビザについても、今後は資本金を500万円→3,000万円に引き上げを検討し、制度の悪用を抑制しようとしています。
最終的には条例(必要であれば法改正)による用途制限や、苦情対応の強化をめざしています。
一方、適正に運営する事業者へは支援拡充をしたり、デジタル監視の導入も進め、暮らしやすさと観光が共に発展でき、安心して共存できるまちづくりを目指します。
4.農業政策
“令和の米騒動”を乗り越え、稼げる農業へ。
2025年、米の価格が高騰し、農家も消費者もいまだ厳しい状況が続いています。昨年、米農家からの卸値は60kg12,000円だったのが、今年は34,000円前後にまで高騰しており、市場に出てくる新米は、これまで以上に高騰することが見込まれます。
米価格がここまで高騰したのにはいくつもの複雑な要因が絡み合っていますが、今の価格でようやく農家も再生産が可能になってきたことを考えれば、一時的な備蓄米放出や輸入拡大では根本解決にはなりません。
一つ一つの農家を、大規模化、高度化して、単価を上げる前に量で利益を確保できる、そうした環境に変えていくことも必要です。
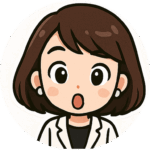
10年後には、後継者が決まらずに今ある農地の3割から4割が、耕作放棄地となってしまう可能性が危惧されています。
そうした農地を集約し、新規就農や革新的技術(AIやドローン)に支援することで、大規模化と高収益化を促し、結果として市場価格を安定化させます。さらには、輸出を促進して稼げる農家を増やしていきます。
中山間地の大規模化が難しい農地については、環境保全、水資源の保全、保水力の維持等、さまざまな機能があることから、農地を守ることに補助はしつつ、温暖化等の気候変動も見据え、さらに高付加価値作物に転換できないか、探っていく必要もあります。
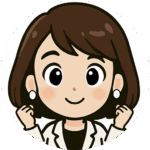
大事な日本の食べ物の、安全と安心を守っていかなければなりません。
5.教育
すべての子どもに、平等な学びの機会を。
日本維新の会が進めてきた高校授業料無償化は、2026年4月から所得制限を撤廃し、すべての高校生(外国人労働者の子どもを含む)が対象となります。
「外国人も対象なのか?」という声もありますが、日本で働き、納税している方々の子どもに教育の機会を保障することは、共生社会の基盤です。ただし、短期滞在者や社会保険料未払いなど一定条件を満たさない場合には、制度運用の見直しも、もちろん必要です。
教育無償化の目的は、親の所得や環境による教育格差をなくすこと。
子どもは生まれた瞬間から平等であり、未来を担う全ての子どもに等しくチャンスを届けたい。それが、私の信念です。

とはいっても、やっぱり外国人のお子さんも無償ってどうなんだろう?
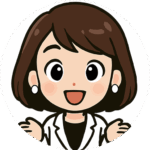
では、少し視点を変えてみませんか?
今や、私たちの身の回りの多くの仕事──建設現場、コンビニ、漁業、介護、農業など──を支えているのは、外国人の皆さんです。
日本の社会はすでに、多くの外国人の力に支えられて成り立っています。
一方で、AIの発達により、ホワイトカラーの仕事が減り、一部の日本人はブルーカラーの職業を選ばなくなりつつあります。そんな中で、外国人労働者が日本を支えてくださっている現実を、
もっと正面から見つめ、感謝と共生の姿勢を持つことが大切だと思います。
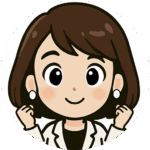
聞こえのよい批判や単純なレッテルではなく、
共に生きるための現実的な議論と制度づくりを進めていきたい──
それが、私の思いです。
最後に
政策ページを最後までお読みいただき、ありがとうございます。
2025年、皆様のご支援に背中を押され、参議院という舞台で活動を始める機会をいただきました。これからは日本が抱える課題にしっかり取り組みながらも、その解決の糸口は地域の皆さまの声の中にあると胸に刻み、全力で努めてまいります。
大阪は新しいことに挑戦し続け、力を合わせて成長してきました。日本の豊かな未来を築くため、これからも挑戦を恐れず有言実行します!